
かつて一世を風靡した六星占術ですが、「六星占術は当たらないのではないか」と感じている方もいらっしゃるかもしれません。そもそも六星占術は当たるのか、特に一時代を築いた細木数子さんの六星占術が当たるという話は本当なのか、気になるところです。
また、六星占術で一体何がわかるのか、そしてなぜ六星占術が当たる(と言われる)のか、その根拠や六星占術の当たる確率についても、様々な疑問が聞かれます。
この記事では、そうした六星占術に関する疑問に多角的に答えていきます。基本的な仕組みや占えることから始め、当たる・当たらない双方の意見、その背景にあるとされる考え方、さらには私たちが占いと上手に付き合っていくためのヒントまで、詳しく解説します。
- 六星占術の基本的な仕組みや占える内容がわかる
- 「当たる」「当たらない」双方の意見とその根拠を知る
- 大殺界など、占いの結果に対する多様な解釈を理解する
- 占いに振り回されず、上手に活用するためのヒントを得る
関連記事:
- 生年月日の占いはなぜ当たる?根拠や心理的なからくりを徹底解説
- 運命数11は強運の持ち主?性格や相性と開運の秘訣
- 運命数33の人に嫌われるとどうなる?起こりうる事態と関係改善方法
- 姓名判断を誰が考えた?明治時代から現代まで続く起源と発展の全貌
🔮 いま占える → 電話占いデスティニー ![]()
六星占術は当たらない?その疑問に答えます
- 六星占術で何がわかるの?占術の基本
- 六星占術は当たるのか?様々な意見を紹介
- 細木数子の六星占術は当たる?継承者の見解
- 六星占術がなぜ当たる?統計学との関係性
- 六星占術の当たる確率って?根拠はある?
六星占術で何がわかるの?占術の基本
六星占術は、私たちが生まれ持った宿命や運勢のリズムを知るための一つの手がかりとなる占術です。具体的には、生年月日から算出される「運命星」と生まれ年の「干支」を基盤として、個人の性格や才能、日々の運気の流れ、さらには他者との相性などを読み解いていきます。
六星占術の成り立ちと仕組み
六星占術は、占い師の細木数子氏が中国古来の易学、算命学、万象学などを基に提唱したとされる占いです。この占術の中心となるのが、以下の6つの「運命星」です。
- 土星人
- 金星人
- 火星人
- 天王星人
- 木星人
- 水星人
これらの運命星は、生年月日から計算される「運命数」によって決まります。さらに、生まれた年が十二支のどれに当たるかによって、各運命星はプラス(陽)とマイナス(陰)に分けられます(例:土星人(+)、水星人(-))。
また、特定の生まれ年(停止の年に該当)の人は「霊合星人」と呼ばれ、本来の運命星と、それと対になる運命星(例:土星人なら天王星人)の両方の影響を受けるとされています。
12種類の運気「占命盤」
六星占術では、運気の流れを12種類の周期で示します。これを「占命盤」と呼び、種まきから収穫、そして次の準備期間へと続く、植物の成長になぞらえられることもあります。
特に「陰影」「停止」「減退」の3年間は「大殺界」と呼ばれ、一般的に新しいことを始めたり、大きな決断をしたりするのは避けた方が良いとされる時期です。しかし、この時期の過ごし方や影響については、様々な解釈があります。
六星占術で占えること
これを踏まえて、六星占術で具体的に何がわかるのかをまとめると、主に以下の点が挙げられます。
- 基本的な性格・性質: 運命星によって、その人が持つ基本的な性格、考え方の傾向、得意なことや苦手なことなどがわかります。
- 年・月・日の運勢: 12周期の運気の流れを知ることで、その年、その月、その日が自分にとってどのような時期なのかを把握できます。これにより、行動を起こすタイミングや注意すべき点を考えるヒントになります。
- 相性: 自分と相手の運命星を組み合わせることで、恋愛、結婚、仕事、友人関係などにおける相性を占うことができます。
- 人生の転機: 大殺界や、逆に運気が良いとされる時期(達成、財成、安定など)を知ることで、人生における注意すべき時期やチャンスの時期を意識することができます。
このように、六星占術は自己理解を深めたり、人生の波を乗りこなすための一つの指針を与えてくれるものです。ただし、占いは未来を断定するものではなく、あくまで可能性や傾向を示すものです。どのように活用するかは、個人の判断に委ねられています。
六星占術は当たるのか?様々な意見を紹介
六星占術って当たるのかな?当たった!って言う人大殺界中と運気良いときどんな感じだったか教えて欲しい~!(ᐡɞ̴̶̷ ̫ ɞ̴̶̷ᐡ)
— くるみ (@kurumi_zzzz) November 27, 2023
六星占術が「当たる」と感じるか、「当たらない」と感じるかは、人によって大きく意見が分かれるところです。ここでは、肯定的な意見と懐疑的な意見、双方の視点から様々な考え方を紹介します。
「当たる」と感じる人の意見
六星占術を支持する人や、実際に「当たった」と感じる経験を持つ人からは、以下のような声が聞かれます。
- 運気の流れが実際の出来事と一致する: 特に「大殺界」の時期に、予期せぬトラブルや体調不良、精神的な落ち込みなどを経験し、「占いの通りだった」と感じる人は少なくありません。逆に、「達成」や「財成」といった運気の良い時期に、目標達成や良い出会いなどがあり、運気の波を実感するという意見もあります。
- 性格診断の的確さ: 自分の運命星が示す性格や才能、考え方の癖などが、自分自身や周りの人の特徴とよく合っていると感じ、「納得できる」という声も多くあります。自己理解の一助となると捉えられています。
- データ分析に基づいた側面: 提唱者である細木数子氏自身や、その娘のかおりさん、また同じく占いを研究するゲッターズ飯田氏などは、六星占術(あるいは自身の占い)を単なる占いではなく「統計学」であると述べています。これは、長年にわたる膨大な人々のデータを分析し、「こういう星(タイプ)の人は、こういう時期に、こういう傾向の出来事が起こりやすい」というパターンを見出した学問である、という考え方です。このアプローチに、一定の信頼性を感じる人もいます。
「当たらない」「信じない」と感じる人の意見
一方で、六星占術に対して懐疑的な見方をする人や、「当たらない」と感じる人も多く存在します。
- 占いの内容が曖昧・一般的: 占いの記述が抽象的であったり、誰にでも当てはまりそうな一般的な内容であったりするため、「当たっているように感じるだけ(バーナム効果)」ではないか、という指摘があります。良いことも悪いことも、解釈次第でどうとでも受け取れるという見方です。
- 科学的根拠の欠如: 占いは科学的に証明されたものではなく、未来を正確に予測することは不可能である、という立場からの意見です。お笑い芸人のカンニング竹山さんのように、「本当に占いが当たるなら、戦争や災害はなくなるはずだ」と、未来予知としての占いを根本的に否定する考え方もあります。
- 実際の経験との不一致: 占いで「大殺界」と言われた時期に結婚して幸せになったり、逆に運気が良いとされる時期に不運が続いたりするなど、占いの結果と実際の人生経験が一致しないケースも多々報告されています。
- 精神安定剤としての役割?: 占いを信じることは、一種の精神安定や拠り所を求める心理の表れであり、宗教的な要素に近いのではないか、という見方もあります。悩みがある時に背中を押してもらったり、漠然とした不安を和らげたりするために利用される側面がある、という考えです。
- 情報の不確かさ: 占いの元となる生年月日自体が、戸籍上のものと実際の出生日が異なるケース(昔の学年調整など)もあり、その場合、占いの結果そのものがズレてしまう可能性も指摘されています(カンニング竹山氏の例)。
どう向き合うか
結局のところ、六星占術が当たるかどうかは、個人の受け止め方や人生経験、価値観に大きく左右されると言えます。
「当たる」と感じる人にとっては、人生の指針や行動のヒントとなり得ますが、「当たらない」と感じる人にとっては、数ある考え方の一つに過ぎないかもしれません。
重要なのは、占いの結果に一喜一憂しすぎず、鵜呑みにしないことです。あくまで参考情報の一つとして捉え、最終的な判断や行動は自分自身の意思で行う、という姿勢が大切ではないでしょうか。
細木数子の六星占術は当たる?継承者の見解
六星占術ってどうしてこうも当たるのか…容赦ないな…
— K (@kw_fierce) December 25, 2020
一世を風靡した占い師、細木数子さんの六星占術。その的中率については様々な意見がありますが、細木さん自身や、現在その占いを引き継いでいる娘のかおりさんは、どのように考えているのでしょうか。
細木数子氏自身のスタンス:「占いではない、統計学だ」
細木数子さんは生前、自身の六星占術について「これは占いではない、統計学だ」と公言していました。また、「未来のことなんて、誰にもわからない」とも断言していたと伝えられています。これは、六星占術が単なる当て物ではなく、長年のデータに基づいた傾向分析であるという考え方を示しています。
彼女の鑑定スタイルは、運命星から導き出される傾向を伝えつつも、それ以上に相談者自身の人間性や生き方に対して、時に厳しく、時に力強いアドバイスを送るというものでした。「地獄に堕ちるわよ!」といった辛口な言葉は、彼女の代名詞ともなりましたが、それは相談者に行動を促したり、考えを改めさせたりするための強いメッセージだったのかもしれません。
テレビ番組などで見せた鋭い指摘やアドバイスが多くの人の心をつかみましたが、一方で、具体的な未来予測や芸能人の運勢占いに関しては、的中したものもあれば、外れたものもあったと言われています。つまり、彼女の人気は、占いの的中率そのものよりも、むしろその強いキャラクターや、人生経験に裏打ちされたようなアドバイスにあったと考えることもできます。
継承者・細木かおりさんの見解
細木数子さんの意思を継ぎ、現在六星占術の継承者として活動しているのは、娘の細木かおりさんです。かおりさんもまた、六星占術は「統計学」であるという基本的なスタンスを受け継いでいます。
母である数子さんから直接指導を受け、マネージャーとしても活動を支えてきた経験から、六星占術の理論や考え方を深く理解し、それを現代に合わせて伝えています。書籍の執筆や講演会、メディア出演、さらにはYouTubeチャンネルなどを通じて、より幅広い層に六星占術を広める活動を行っています。
かおりさんの語り口は、母・数子さんと比較すると穏やかであると言われますが、六星占術が示す運気の流れや、各運命星の持つ性質に基づいたアドバイスを行う点では共通しています。彼女もまた、占いの結果を伝えるだけでなく、それをどのように人生に活かしていくか、という視点を大切にしているようです。
このように、提唱者である細木数子氏も、その後継者であるかおりさんも、六星占術を単なる未来予知ではなく、過去からのデータに基づく傾向分析、すなわち「統計学」として捉えている点が特徴的です。当たる・当たらないという二元論ではなく、人生をより良く生きるための知恵や指針として活用することを推奨していると言えます。
六星占術がなぜ当たる?統計学との関係性

六星占術が「当たる」と感じる人がいる背景には、この占術が持つ「統計学」的な側面が関係していると考えられます。提唱者である細木数子氏をはじめ、関係者は六星占術を単なる占いではなく、長年のデータ分析に基づいた学問であると位置付けています。
膨大なデータから導き出す「傾向」
「統計学」であるという主張の根拠は、過去の膨大な人々の人生データや鑑定記録に基づいている点にあります。具体的には、生年月日によって決まる「運命星」を持つ人々が、どのような性格的特徴を持ち、どのような運気の波を経験しやすいのか、というパターンを分析・集積したものとされています。
例えば、多くの人々を鑑定し、その記録を詳細に分析することで、「Aという運命星の人は、Xという時期に成功しやすい傾向がある」「Bという運命星の人は、Yという状況で困難に直面しやすい」といった、一定の法則性のようなものが見出される、という考え方です。これは、現代のデータサイエンスにおける傾向分析にも通じる部分があるかもしれません。
実際に、占い師の中には、独自に何万人もの鑑定データをノートに記録し、そこから法則性を見出そうと研究を重ねている人もいると言われます。ゲッターズ飯田氏なども、自身の占いを「統計学」と呼び、徹底的なデータ収集と分析に基づいていることを強調しています。
古代からの知恵の集積?
また、六星占術のベースとなっている易学や算命学といった東洋の占術自体が、非常に長い歴史を持っています。これらは、古代中国において、自然界の観察や人間の営みに関する膨大な経験則、知恵が集積され、体系化されたものと考えることができます。
季節が巡り、自然現象が繰り返されるように、人間の運命にも一定のリズムやパターンがあるのではないか。そのような考えに基づき、生年月日という普遍的な情報から、個人の持つ宿命や運勢の傾向を読み解こうとしたのが、これらの占術の根源にあるのかもしれません。
統計学=未来予測ではない
ただし、ここで言う「統計学」は、学術的な意味での厳密な統計学とは異なる可能性があります。あくまで、過去のデータから見出された「傾向」を示すものであり、個々人の未来を100%正確に予測したり、運命を決定づけたりするものではありません。
人間の人生は、持って生まれた宿命だけでなく、その後の環境、本人の選択、努力、そして偶然の出来事など、様々な要因が複雑に絡み合って形作られます。したがって、六星占術が示すのは、あくまで可能性の一つ、あるいは注意すべき傾向として捉えるのが適切でしょう。
「統計学」という言葉を使うことで、占いに客観性や信頼性を与えようとしている側面もあるかもしれませんが、それによって「当たる」と感じるメカニズムの一端を説明しているとも言えます。
六星占術の当たる確率って?根拠はある?
昔流行った六星占術(細○数子の) たまにふっと調べて見るんだけど、今年全然良い年なんだけど月別に見ると5月〜7月で大殺界なんですよな
人間関係がやばい人間関係に注意とか書いてあって「まさに〜~~~~~~~?!」てなってる 当たるのか…— てぃん✨ (@xxxtinxxx) June 10, 2022
六星占術の「当たる確率」について、具体的な数値を出すことは非常に困難であり、科学的な根拠は認められていません。占いが当たるかどうかは、客観的な確率の問題というよりも、個人の主観的な解釈や心理的な要因が大きく関わっています。
なぜ「当たる」と感じるのか?
占いが当たると感じる背景には、いくつかの心理的なメカニズムが働いている可能性があります。
- バーナム効果: 占いの記述には、誰にでも当てはまりそうな、一般的で曖昧な表現が多く含まれることがあります。「あなたは時々、自分の決断に自信が持てなくなることがあるでしょう」といった記述は、多くの人が「自分のことだ」と感じやすいものです。このように、自分に向けられた性格分析などが、実際には多くの人に当てはまるにも関わらず、自分に特有のものだと認識してしまう心理効果をバーナム効果と呼びます。
- 確証バイアス: 人は、自分が信じていることや期待していることを裏付ける情報ばかりを探し求め、それに反する情報は無視したり、軽視したりする傾向があります。占いが当たった経験は強く記憶に残りやすい一方で、外れた経験は忘れがちになる、ということが起こり得ます。これにより、「占いはよく当たる」という印象が強化される可能性があります。
- 自己成就予言: 「今年は運気が良い」と占いで言われると、ポジティブな気持ちになり、積極的に行動した結果、良い成果が得られることがあります。逆に「大殺界だから注意が必要」と言われると、無意識のうちに慎重になったり、ネガティブな出来事に目が行きやすくなったりして、結果的に占いの通りになったかのように感じることがあります。このように、予言や期待が、その後の行動に影響を与え、結果として予言通りの現実を作り出してしまう現象です。
確率や根拠を求めることの難しさ
科学的な視点から見ると、占いの効果や的中率を客観的に測定し、証明することはできません。個人の未来は、あまりにも多くの要因によって左右されるため、生年月日だけで正確に予測することは不可能と考えられています。
例えば、コインを投げて表が出る確率は50%ですが、これは偶然の結果です。六星占術の的中率が、この偶然の確率を有意に上回ることを示す客観的なデータや研究は、一般的には存在しません。
芸能人の結婚や成功を言い当てた、あるいは外した、といったエピソードが話題になることもありますが、それはあくまで個別の事例であり、全体の「当たる確率」を示すものではありません。
占いとの向き合い方
六星占術に限らず、占いの「当たる確率」や「科学的根拠」を追求することには限界があります。むしろ、占いをどのように捉え、どのように活用するかが重要になると言えます。
占いは、以下のような目的で利用されることがあります。
- 自己理解のツール: 自分の性格や才能を知るきっかけにする。
- 意思決定の参考: 何かを選ぶ際に、後押しや注意喚起として参考にする。
- 行動のきっかけ: ポジティブな占い結果を励みに、新しいことに挑戦する。
- 心の拠り所: 不安な時に、安心感を得たり、前向きな気持ちになったりする。
このように、占いを絶対的なものとして盲信するのではなく、人生を豊かにするための一つのヒントやツールとして、上手に付き合っていくことが大切です。最終的な判断は常に自分自身で行い、占いに振り回されない主体性を持つことが求められます。
六星占術が当たらないと感じる理由とは?

- 六星占術が当たってないと感じる人の声
- 六星占術を信じない派の意見とは?
- 大殺界は当たらない?影響を受けない人も
- 占いは当たる?当たらない?心理的効果
- 占いとの上手な付き合い方とは
六星占術が当たってないと感じる人の声
六星占術は多くの人に影響を与えていますが、一方で「占いの通りにならなかった」「当たっていない」と感じる人も少なくありません。ここでは、具体的にどのようなケースで「当たっていない」と感じるのか、様々な声を紹介します。
運気の流れと現実のギャップ
六星占術では、12年周期の運気の流れがあり、特に「大殺界(陰影・停止・減退)」は注意が必要な時期とされています。しかし、この運気の流れと実際の人生経験が一致しないという声が多く聞かれます。
- 「大殺界」に良い出来事があった: 一般的に運気が低迷するとされる大殺界の時期に、むしろ人生における大きな幸運や転機を迎えたという経験を持つ人がいます。例えば、理想の相手と出会い結婚した、希望通りの転職が成功した、念願のマイホームを購入できた、といったケースです。占いで悪い時期とされていたにも関わらず、結果的に充実した期間を過ごしたため、「占いは当てにならない」と感じるようです。
- 運気の良い時期に不運が続いた: 逆に、「達成」や「財成」といった運気が最高潮とされる年に、予期せぬ不運に見舞われたという人もいます。大切な人との別れ、失業や経済的な困窮、病気や事故、家族の問題など、辛い出来事が重なり、「占いは全く当たらなかった」と感じるケースです。期待していただけに、裏切られたような気持ちになることもあるかもしれません。
性格診断や相性占いとの不一致
六星占術では、運命星に基づいた性格診断や、相手との相性を占うこともできますが、これらについても「当たっていない」と感じる場合があります。
- 性格診断がしっくりこない: 自分の運命星から導き出される性格の特徴が、自分自身の性格や考え方とは異なると感じるケースです。「冷静でクール」とされているのに実際は情熱的だったり、「家庭的」とされているのに仕事中心の生活を送っていたりするなど、ギャップを感じることがあります。
- 相性占いが現実と違う: 占いで「相性が最悪」とされた相手と、実際には長年の親友であったり、円満な夫婦関係を築いていたりする場合があります。逆に、「最高の相性」と言われた相手と、すぐに破局してしまったり、人間関係で苦労したりするケースも聞かれます。
その他の要因
年単位の運気だけでなく、月単位の運勢についても、「当たっている実感がない」という声があります。特定の月が毎年運気が悪いとされることに対して、「たまたまかもしれないし、気にしすぎているだけかもしれない」と感じる人もいます。
このように、六星占術の示す内容と、自身の実際の人生経験との間にずれが生じた場合に、「当たっていない」と感じることが多いようです。こうした経験から、占いの結果に一喜一憂するのではなく、自分の感覚や現実を大切にしようと考えるようになる人もいます。
六星占術を信じない派の意見とは?
六星占術の日運て当たるのかな?
前は少し頼りにしてたけど、その時の自分の感情故の行動と噛み合わない気がしてきた。— 盛山酒🐱凍結が解凍されたら春だった (@Incidentaccide) June 22, 2021
六星占術を含む占い全般に対して、懐疑的な立場を取り、「信じない」と考える人々もいます。その理由は多岐にわたりますが、主に以下のような意見が挙げられます。
科学的根拠の欠如と未来の不確実性
最も根本的な理由として、占いに科学的な根拠がないという点が挙げられます。
- 未来予測の不可能性: 人間の未来は、本人の意思決定、努力、環境、偶然など、無数の要因が複雑に絡み合って決まるものであり、生年月日などの限られた情報だけで正確に予測することは不可能である、という考え方です。もし本当に未来がわかるなら、なぜ戦争や災害を防げないのか、という疑問も提示されます。
- 非科学的なアプローチ: 占星術や六星占術で用いられる星の配置や運命星といった概念は、天文学や物理学などの科学的な法則とは異なります。そのため、科学的な思考を重視する立場からは、占いは非合理的なものと見なされます。
「統計学」という主張への疑問
六星占術などが「統計学」であるという主張に対しても、疑問の声があります。
- 学術的統計学との違い: 占いにおける「統計学」は、学問分野としての統計学のように、客観的なデータ収集方法、分析手法、検証プロセスなどが明確に示されているわけではありません。そのため、その信頼性に疑問が持たれることがあります。
- 人間観察力の範疇?: 長年の経験や人間観察力があれば、ある程度の性格や行動の傾向を推測することは可能です。占いは、そうした経験則を体系化したものに過ぎず、特別な力によるものではないのではないか、という見方もあります。
心理的な側面への着目
占いが「当たる」ように感じるのは、心理的な効果が大きいと考える人もいます。
- バーナム効果・確証バイアス: 前述の通り、誰にでも当てはまるような曖昧な表現を自分特有のものと捉えたり、自分の信じたい情報だけを受け入れたりする心理が働くことで、占いが当たっているように感じやすいと指摘されます。
- 精神安定剤としての役割: 悩みや不安を抱えている時に、占いに頼ることで安心感を得たり、決断の後押しを求めたりする心理があるのではないか、という見方です。これは、ある種の「処方箋」や「精神安定剤」のような役割を果たしているだけであり、占い自体に未来を変える力があるわけではない、と考えられています。答えは自分の中にあるにも関わらず、外部の力(占い)にそれを求めてしまう傾向を指摘する声もあります。
自由意志と自己決定の尊重
「自分の人生は自分で決める」という価値観を重視する立場からは、占いは受け入れられません。
- 運命は変えられる: 運命はあらかじめ決められたものではなく、自分自身の選択と行動によって切り開いていくものだと考えます。そのため、占いに頼って行動を制限されたり、可能性を狭めたりすることは避けるべきだと主張します。
- 主体性の重要性: 占いを信じるかどうかに関わらず、最終的な判断は自分自身で行うべきであり、その責任も自分で負うべきだという考え方です。
これらの理由から、六星占術やその他の占いを信じない、あるいは距離を置くという立場を取る人々がいます。彼らは、占いをエンターテイメントとして楽しむことはあっても、人生の重要な決定を委ねることはしない傾向にあります。
大殺界は当たらない?影響を受けない人も
六星占術運勢は特に当たらないので大丈夫です
— かみしまあきら🐰 (@7menzippo) January 14, 2025
六星占術の中でも特に広く知られ、ある種の恐れをもって語られることもある「大殺界」。この期間は運気が著しく低下し、何をやってもうまくいかない時期とされがちです。しかし、実際には「大殺界なんて当たらなかった」「特に悪い影響はなかった」と感じる人も少なくありません。なぜそのような違いが生まれるのでしょうか。
「大殺界」の本来の意味合い
まず考えられるのは、「大殺界」という言葉のイメージが先行し、その意味合いが誤解されている可能性です。
- 「最悪の時期」とは限らない? 大殺界は、必ずしも全ての物事が破綻するような最悪の時期を意味するわけではない、という解釈があります。むしろ、「幸運な出来事が起こりにくくなる時期」「実力以上の結果が出にくい時期」「これまでの行いの結果が表れやすい時期」といった捉え方です。つまり、運気の後押しが期待できない分、地道な努力や本来の実力が試される期間とも言えます。
- 膿を出す時期? また、大殺界はこれまでに溜まった問題点や不摂生などが表面化しやすい時期とも考えられます。例えば、不健康な生活を続けていた人が病気になったり、人間関係の歪みが露呈したりすることがあるかもしれません。しかし、これは見方を変えれば、問題に気づき、改善するきっかけを与えられているとも言えます。いわば、人生の「膿を出す」デトックス期間のようなもの、と捉えることもできるでしょう。
影響を受けにくいとされる人の特徴
興味深いことに、「普段からの行いや心構えが良い人は、大殺界の影響を受けにくい」という考え方があります。
- 感謝と謙虚さ: 日頃から周囲の人々や物事、さらには目に見えない存在(ご先祖様など)への感謝の気持ちを持ち、謙虚な姿勢で過ごしている人は、人から恨みを買ったり、足を引っ張られたりすることが少ないと考えられます。そのため、運気が下降局面にあっても、大きなトラブルに見舞われにくい、というのです。
- 普段の行いの結果: 逆に、大殺界に悪いことが起こる人は、それまでの自分の言動(感謝を忘れる、傲慢になる、人を傷つけるなど)が原因となっている可能性がある、という厳しい見方もあります。その場合、大殺界は自らの行いを反省し、改めるための機会とも言えるかもしれません。
統計的なズレと個人の状況
前述の通り、六星占術が統計的な傾向を示すものだとしても、それは全ての人に100%当てはまるものではありません。個々人の人生の状況やバイオリズムは多様であり、占いの示すパターンから外れることは当然起こり得ます。
たまたま大殺界の時期が、その人の人生においては大きな飛躍のチャンスであったり、逆に安定した時期であったりすることは十分に考えられます。実際に、大殺界の期間中に結婚して幸せな家庭を築いている人や、事業で成功を収めた人もいます。
結論として
このように見てくると、「大殺界」の影響は、その人の状況、これまでの生き方、そして物事の捉え方によって大きく変わってくると言えそうです。「大殺界だから何もできない」と過度に恐れる必要はなく、むしろ自己を振り返り、足元を固めるための期間と捉えることも可能です。また、周りの意見や占いの結果に左右されすぎず、自身の感覚を大切にすることも重要でしょう。
占いは当たる?当たらない?心理的効果
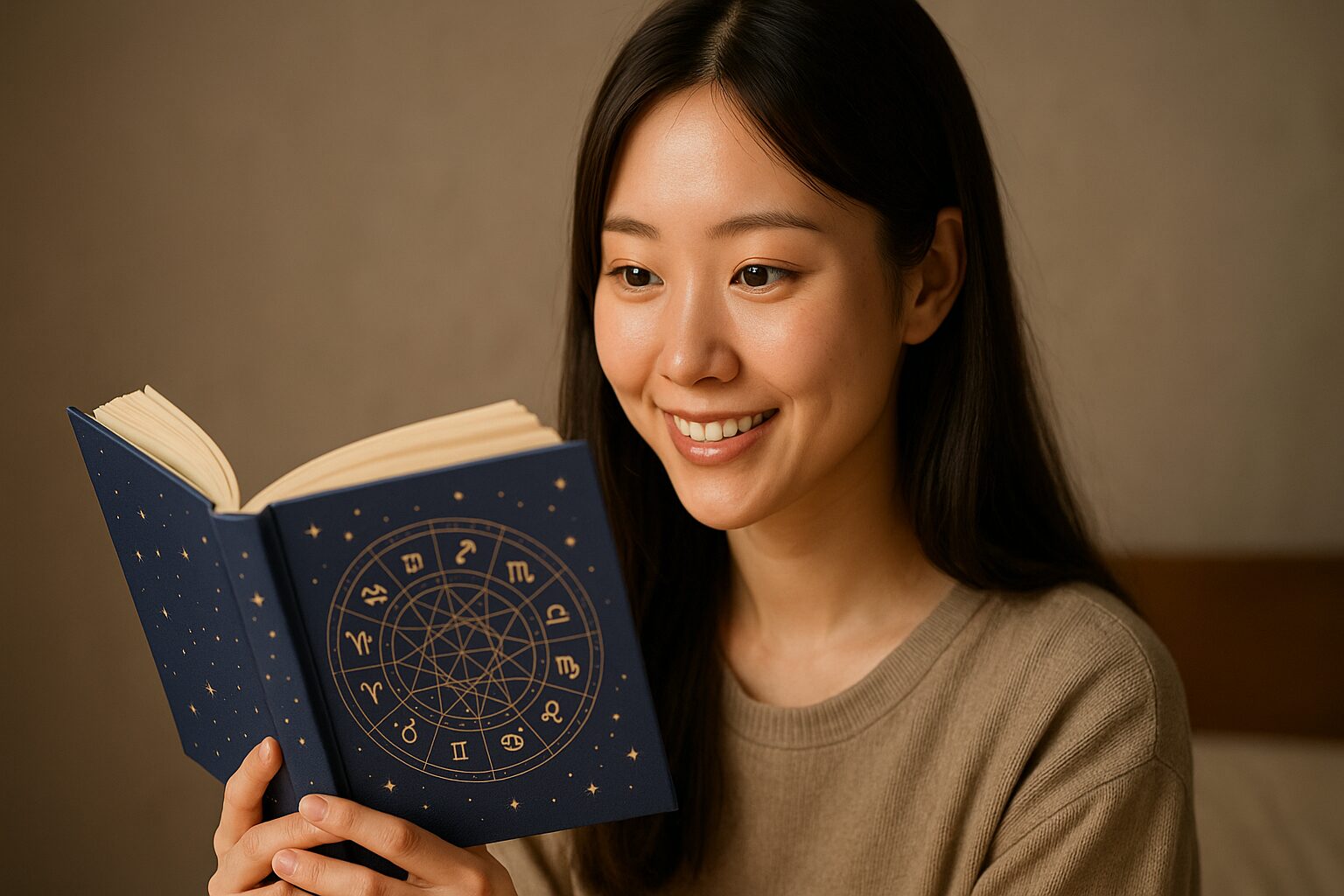
「占いは当たるのか、それとも当たらないのか」という問いは、古くから多くの人々が関心を寄せてきたテーマです。科学的な証明が難しいこの問題において、「心理的な効果」が無視できない役割を果たしていると考えられています。つまり、占いが「当たる」と感じる背景には、私たちの心の働きが大きく関わっているのです。
当たっているように感じる心のメカニズム
なぜ、科学的根拠が乏しいとされる占いでも、「当たる」と感じてしまうのでしょうか。そこには、以下のような心理的な要因が働いている可能性があります。
- バーナム効果: これは、誰にでも当てはまりそうな、曖昧で一般的な性格描写や運勢の記述を、あたかも自分だけに特有のものとして受け取ってしまう心理効果です。「あなたは外向的に振る舞っていても、内面には繊細な部分を隠し持っていますね」といった言葉は、多くの人が「その通りだ」と感じやすい典型例です。占いの多くは、この効果を利用しやすい表現を用いている場合があります。
- 確証バイアス: 人は、自分の考えや信念を支持する情報ばかりを集め、それに反する情報は無視したり、過小評価したりする傾向があります。占いが当たった時の記憶は鮮明に残りやすい一方で、外れた時の記憶は薄れがちです。このため、「あの占いはよく当たった」という印象が積み重なり、「占いは当たるものだ」という信念が強化されていくことがあります。
- 自己成就予言: 占いの結果を信じることで、その後の行動が無意識のうちに変化し、結果的に占いが現実のものとなる現象です。例えば、「今月は恋愛運が良い」と信じれば、積極的に出会いの場に出かけたり、異性に対してオープンになったりして、実際に恋人ができる可能性が高まるかもしれません。逆に、「運気が悪いから失敗するだろう」と思っていると、挑戦をためらったり、些細なミスを過剰に気にしたりして、本当にうまくいかなくなることもあり得ます。
- 暗示効果(プラセボ効果): 占いを信じること自体が、一種の暗示として作用し、心理的な安心感や希望をもたらすことがあります。心が安定することで、物事に対して前向きに取り組めるようになり、結果的に良い方向へ進む(あるいは、そう感じられる)ことがあります。これは、薬効のない偽薬でも効果が現れるプラセボ効果と似たメカニズムです。
- 後付けによる解釈: 何かが起こった後で、「そういえば、占いでこんなことを言われていたな」と思い出し、出来事を占いの内容に結びつけて解釈することで、「当たっていた」と感じることもあります。
心理効果を理解する意味
これらの心理効果は、占いの不思議さや魅力を説明する一因となりますが、決して占いを否定するものではありません。むしろ、占いがなぜ人々の心に響き、影響を与えるのかを理解する手がかりとなります。
自分が占いを信じやすいタイプなのか、どのような心理が働きやすいのかを知っておくことで、占いの結果に振り回されることなく、より客観的に、そして建設的に占いと付き合っていくことができるようになるでしょう。
占いとの上手な付き合い方とは
六星占術って当たるのかなぁ。ズバリ言うわよ~
— ちゃみぴす (@chamipisuuuu) November 7, 2018
占いは、私たちの悩みや迷いに寄り添い、時に指針を与えてくれる魅力的なツールですが、その一方で、依存してしまったり、結果に振り回されたりする危険性もはらんでいます。では、私たちは占いとどのように付き合っていくのが賢明なのでしょうか。
占いを「ツール」として活用する視点
まず大切なのは、占いを「絶対的な未来予知」や「運命の決定書」としてではなく、あくまで「人生をより良く生きるためのツール(道具)」の一つとして捉えることです。道具は使い方次第で良くも悪くもなります。
- 目的意識を持つ: なぜ占いをしたいのか、占いに何を求めているのか(自己分析、決断の後押し、不安解消、単なる楽しみなど)を自分の中で明確にしておきましょう。目的がはっきりしていれば、結果の受け止め方も変わってきます。
- 参考情報と割り切る: 占いの結果は、数ある情報の中の一つとして捉え、鵜呑みにしないことが肝心です。最終的な判断や行動は、他の情報(客観的な事実、専門家の意見、信頼できる人のアドバイスなど)も考慮に入れ、自分自身の責任において行いましょう。
- 結果の解釈は柔軟に: 良い結果が出た場合は、それを自信や行動へのエネルギーに変えましょう。一方、悪い結果が出た場合は、「気をつけよう」「準備しておこう」という注意喚起として受け止め、過度に落ち込まないようにします。悪い結果を回避するためのヒントと捉えることもできます。
- 依存しない距離感を保つ: 「占いがなければ何も決められない」という状態は健全ではありません。占いはあくまで補助的なものと考え、自分の頭で考え、判断する力を失わないようにしましょう。困ったときに時々参考にする、くらいの距離感が良いかもしれません。
- 多角的な視点を持つ: 特定の占術や一人の占い師の意見に偏らず、様々な情報源に触れることも大切です。異なる視点を知ることで、よりバランスの取れた判断が可能になります。
- エンターテイメントとして楽しむ: 雑誌の星占いやテレビの占いコーナーなどは、あまり深刻に捉えず、コミュニケーションのきっかけや、日常のちょっとしたスパイスとして楽しむ、という姿勢も時には必要です。
- 自分の直感を大切にする: もし占いの結果が自分の感覚や直感と異なる場合は、無理に占いに合わせる必要はありません。「何か違うな」と感じたら、自分の内なる声を信じる勇気も持ちましょう。「答えは自分の中にある」ことが多いものです。
- 行動を止めない言い訳にしない: 「運気が悪いから今は動けない」という考えに囚われすぎると、大切なチャンスを逃してしまう可能性があります。どんな時期であっても、自分にできることを見つけ、前向きに取り組む姿勢が、結果的に良い流れを引き寄せることもあります。
注意すべき点
中には、相談者の不安を過度に煽ったり、高額な物品(印鑑、数珠、墓石など)の購入を勧めたりする悪質なケースも存在します。少しでも「おかしいな」と感じたら、安易に信じ込まず、距離を置くようにしましょう。
占いとの付き合い方に絶対的な正解はありません。大切なのは、自分にとって最も心地よく、建設的で、主体性を失わない関わり方を見つけることです。上手に活用すれば、占いはあなたの人生を豊かに彩る味方となってくれるでしょう。
総括:六星占術は当たらない?理由と根拠、確率まで徹底解説します
この記事をまとめると、
- 六星占術は生年月日から運命星を基に占うものである
- 性格・運勢リズム・他者との相性などを読み解くとされる
- 12種類の運気周期があり「大殺界」が特に知られる
- 六星占術が当たるか否かは肯定・否定の両意見が存在する
- 当たる派は運気と現実の一致や性格診断の的確さを挙げる
- 当たらない派は内容の曖昧さや科学的根拠の欠如を指摘する
- 提唱者の細木数子氏らは占いではなく「統計学」と主張した
- これは長年のデータに基づく傾向分析という考え方である
- ただし学術的な統計学としての厳密な証明はない
- 当たる確率を示す客観的データや科学的根拠は未確立である
- 心理的効果(バーナム効果等)が「当たる」感覚に影響する
- 大殺界に良い事があった等、占いと現実が一致しない声もある
- 大殺界の影響は個人差があり、普段の行いが関係するとの説もある
- 占いを信じない人々は科学的合理性や自己決定を重んじる
- 占いは未来の決定ではなく参考情報として活用するのが望ましい